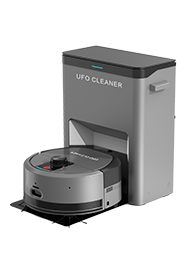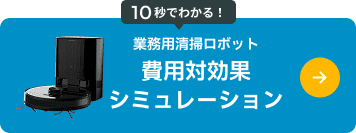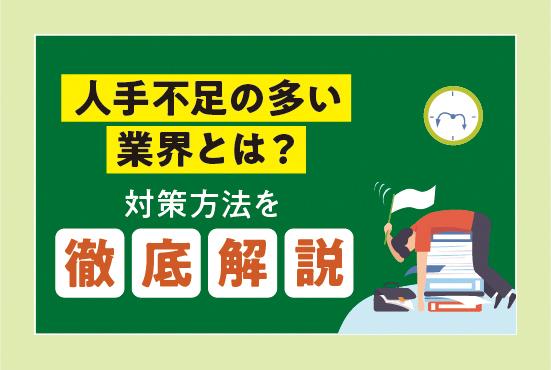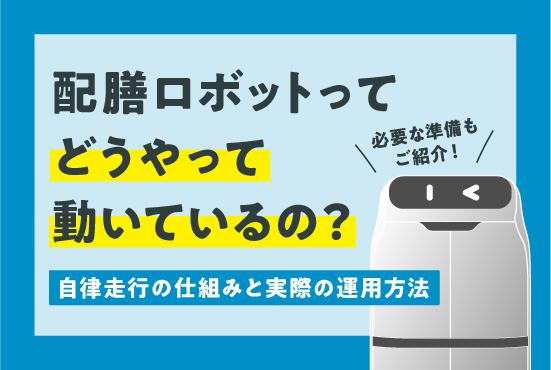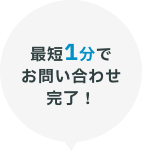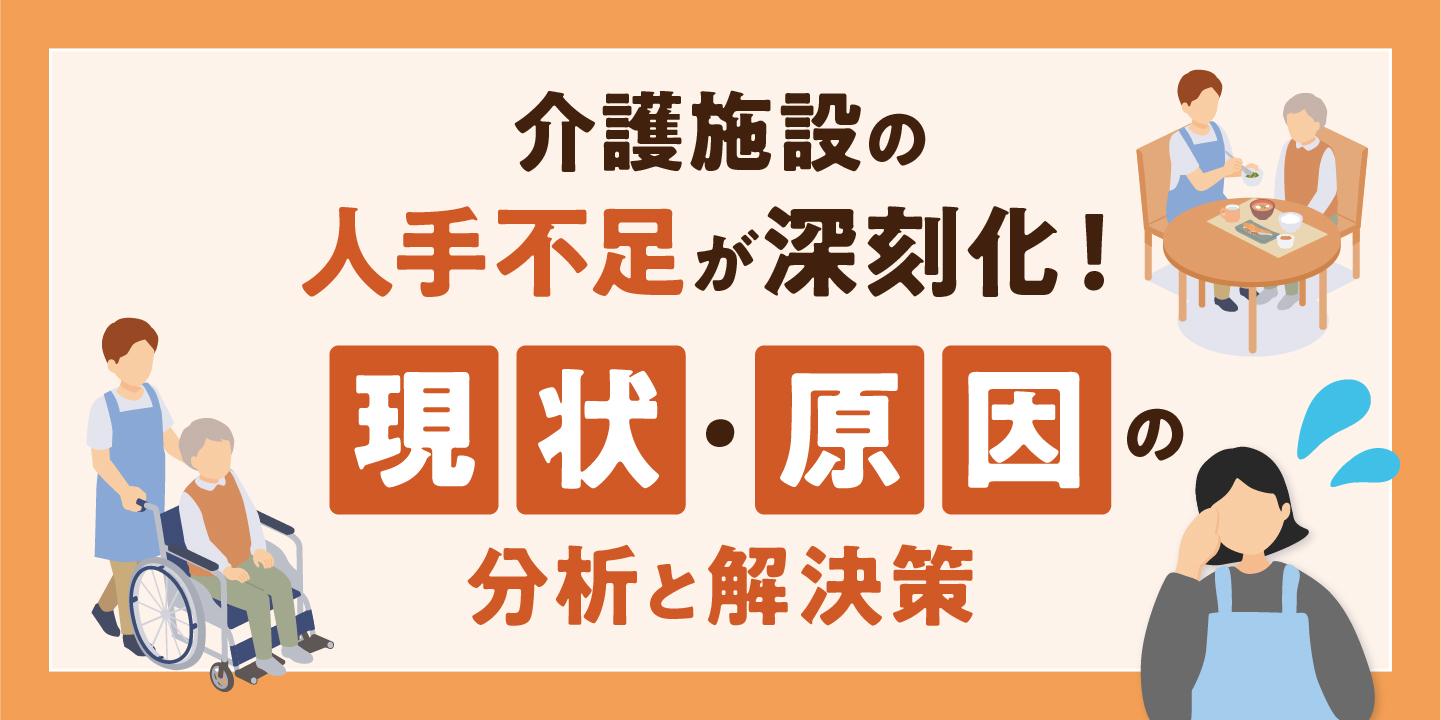
介護施設の人手不足が深刻化!データに基づく現状・原因の分析と解決策
2025.05.21 (更新日:2025.05.30)
目次
介護業界は、人手不足が深刻化している業界の代表格であり、実際に閉鎖へ追い込まれる事業所が増加しています。その背景にある社会的・構造的な問題や、増え続ける介護需要を踏まえると、介護施設における組織体制の改革および業務改善が喫緊の課題です。
今回は、データ分析の結果に基づく介護施設の人手不足の原因と、その解決策を解説します。
データからみる介護施設の人手不足の現状

まず、2025年時点の最新データを基に、介護施設の人手不足の現状を説明します。
介護人材の不足数
厚生労働省が実施した「介護サービス施設・事業所調査」によると、介護保険給付の対象施設に従事する2023年度の職員数は約212.6万人です。対して、同年における要介護および要支援認定者数は約705万人でした。
したがって、介護人材の不足数は492.4万人です。前年より減少傾向にはあるものの、ニーズに対して人手がまったく足りていない状況だといえます。
閉鎖した介護施設の数
株式会社東京商工リサーチの調査では、2024年における老人福祉・介護事業全体の倒産・休廃業数は、過去最多となる784件だったことが分かりました。最も顕著なのは訪問介護の分野ですが、通所・短期入所施設や有料老人ホームでも、前年と比べ休廃業が増加しています。
また現時点では休廃業中でも、物価が高騰する現代では今後倒産となる可能性が否めません。介護業界は、依然として厳しい状況が続くでしょう。
介護職の有効求人倍率
厚生労働省がまとめた「一般職業紹介状況」によると、令和2024年12月における介護サービス職業従事者の有効求人倍率は4.25倍でした。なお有効求人倍率とは、当月およびその前月から繰り越された求職者(有効求職者数)1人あたりの求人件数の割合です。全業種の合計が1.22倍であることを踏まえると、介護業界は求人数に対して求職者が圧倒的に少ないことが伺えます。
介護施設における人手不足の原因

介護施設における「人手不足」には、単なる数の不足だけではなく、現場の中核としての役割を担う人材の確保が難しいという意味も含まれています。次は、介護施設の人手不足の原因について、人数・人材の2つの側面から考えていきましょう。
スタッフの人数が足りない
先述のとおり、介護施設の多くが運営およびサービス提供に必要な人員数が足りていない、もしくは業務が辛うじて回せる人手しかいない状況です。これでは円滑な運営が難しいうえ、一人あたりの業務負担も重く、スタッフのさらなる離職を招く原因になりかねません。
また人数自体は足りていても、介護保険制度に定められる介護専門職の有資格者の人数や、将来的に業務の中核を担う新人スタッフの不足という側面もあります。スタッフのスキルアップを図ろうにも、最低限の人員すら十分でないと、従業員教育に回す時間的な余裕がありません。このままでは、いずれ運営が立ち行かなくなる恐れがあります。
優秀な人材が足りない
現在の介護施設で意外に多い課題が、人材の不足です。職員の人数自体は足りていても、そのうち十分なスキルを持つ従業員はごくわずかという状況です。また業務内容および勤務時間が限定的なパートタイマーが多く、長時間にわたり柔軟に働けるスタッフが少ないというケースも少なくありません。
従業員ごとの介護の知識やスキルの差が大きいと、提供するサービスの質が不均一になります。さらに特定の人材へ負担が偏るほか、業務が属人化しやすい点も問題です。特定の人材が休暇や休職・退職などで現場を離れると、施設の業務が一気に回らなくなるリスクがあります。
人手不足で仕事が回らない介護施設が多い背景にある構造的な問題点

介護施設における人手不足が深刻化している背景には、業界全体にかかわる次の3つの構造的問題があります。
- 少子高齢化
- 過酷な労働環境
- 給与の低さ
少子高齢化
現代の日本は、深刻な少子高齢化の時代です。現役世代が少ない一方で、介護に対する需要は高まっており、人材獲得競争が激化しています。
政府によると、日本における65歳以上の割合は2040年で約35%、2070年には39%に達する予測です。対して15〜64歳以下の人口は1970年頃から徐々に減少しており、合計特殊出生率も諸外国と比べ最低水準にとどまっています。
したがって、国内における平均寿命の延びにより、介護を必要とする人が増える中で、働き手が圧倒的に足りないという状況が長期的に続く可能性が高いでしょう。
過酷な労働環境
介護職は、心身ともに重労働だといえる職種の一つです。
現場業務の大半が肉体労働であり、場合によっては夜勤も必要になります。実際に、腰痛といった健康上の理由から離職する職員も少なくありません。
また業務内容にくわえ、利用者や同じ職場で働くスタッフなどとの人間関係によるストレスも深刻だといえます。厚生労働省がまとめた資料によると、介護職員に最も多い離職理由が職場の人間関係の問題です。
そうした過酷な労働環境が、介護職にチャレンジする際の大きなハードルとなり、人手不足をますます加速させています。
給与の低さ
介護職は、過酷な労働環境にもかかわらず、給与水準が他業種と比べて低い仕事です。厚生労働省の調査によると、介護職員の平均給与額は2022年9月時点で317,540円でした。年収に換算すると、400万円に達しません。同年の全給与所得者の平均給与が458万円であることを踏まえると、介護職員の年収の低さが伺えます。
また、勤続年数が1年と10年以上の介護職員の給与差は60,000円程度しかありません。有資格者になっても、無資格者との給与差は約50,000円です。スキルや経験を積んでも思うような昇給は見込めないことも、若手・未経験の人材が介護職にネガティブなイメージを抱く一因になっています。
介護施設の人手不足を解決する3つの方法

介護施設の人手不足の解決策として、次の3つの方法が挙げられます。
1.幅広い人材を積極的に受け入れる
2.従業員のリスキリングを推進する
3.DXによる業務改善を進める
1.幅広い人材を積極的に受け入れる
人手が足りない介護施設においては、従来の垣根を取り払った幅広い人材採用が求められます。例えば、未経験の方や結婚・育児および介護といった理由で離職中の方、外国人など、幅広い人材を受け入れることで、人員の不足を解消できる可能性があります。
特に外国人の介護人材の受け入れは、国を挙げて推進されている事業の一つです。在留資格「介護」で働く外国人を増やすため、枠組み・制度の整備や業務のあり方などのガイドラインの整備が進んでいます。
採用の幅を広げ、多様なスタッフが働きやすい環境を整えることで、より多くの人材が確保できるようになるでしょう。
2.従業員のリスキリングを推進する
人材の不足を解決するには、従業員のリスキリング促進が有効な手段だといえます。リスキリングとは、業務上で必要となるより高度な知識やスキルを身につけることです。
スタッフ一人ひとりが介護資格を取得などでスキルアップすれば、業務の質の向上および効率化が実現し、人数の不足が補えます。また人は、自身の成長の機会を積極的に提供する存在に対し、信頼感や愛着を抱くものです。施設主導でリスキリングを推奨すれば、従業員のモチベーションアップにつながり、一人あたりの生産性の向上が図れます。
リスキリングは、経済産業省や厚生労働省が推進する事業の一つです。企業・事業所に対する補助・助成制度も設けられているので、予算の問題からリスキリング推進が難しい場合は活用するとよいでしょう。
3.DXによる業務改善を進める
人手不足が深刻化・長期化する現代の介護業界で生き残るためには、省人化および効率化による業務改善が不可欠です。各種管理のプロセスをシステム化するほか、業務へのサービスロボットの導入が推奨されます。
例えば、これまで人が行っていた食事の配膳や清掃をロボットに代替させれば、少ない人手で業務を回すことが可能です。スタッフの負担が軽減し、人の手を高度な業務へ集中させられるほか、空いた時間で教育・研修などの時間も捻出できるようになるでしょう。また、ヒューマンエラーやスタッフによる業務の質の差もなくなるため、業務効率が大きく向上します。
人手不足の介護施設を救う「ROBOTI」の配膳・清掃ロボット
介護施設への配膳・清掃ロボットの導入を検討しているならぜひ「ROBOTI(ロボティ)」へ。ここからは、弊社のサービスおよび業務用配膳・清掃ロボットのおすすめポイントを紹介します。
ROBOTIの特長
「ROBOTI」は、主に次の2つの理由から、多くの企業・事業所の方に選ばれています。
- 多彩なラインアップ
- 選定から導入まで一気通貫のサポート体制
弊社の業務用配膳・清掃ロボットの品揃えは業界トップクラス。メーカー直販価格でリーズナブルな「RACLEBO(ラクリボ)」シリーズをはじめとする多彩な機種をご用意しています。
また導入の際は、選定から現場への設置、操作指導および保守サポートまでワンストップでサポート。トライアルで効果を実感してから導入できるので安心です。
そのほか、レンタルや補助金・助成金申請のアドバイスなど、初期費用が抑えられるサービスも充実。業界ごとの課題にも精通しているので、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。
介護施設の人手不足解消にROBOTIが貢献した事例
続いて、人手不足を抱える介護施設への導入実績を紹介します。
「株式会社福祉ネットワーク研究所」様の事例

人手不足による清掃時間の確保が難しいことから、業務用清掃ロボットの導入を検討していた「株式会社福祉ネットワーク研究所」様。「自社に最適な機種の選び方が分からない」というご相談を受け、2種類の業務用清掃ロボットをご提案。予算内に収まるのはもちろん、丁寧なヒアリングや、適材適所の清掃ロボットの導入にご満足いただけました。
「おぎくぼ紫苑」様の事例

業務効率化および従業員の負担軽減という課題を抱えていた「おぎくぼ紫苑」様。メーカー直販でリーズナブルな「RACLEBO」の提案と、東京都の補助金申請に関するアドバイスにより、予算内で3台の清掃ロボットの導入が実現しました。業務用清掃ロボットの活用により、夜間の作業が可能になったことで、課題解決に成功したとの声が寄せられています。
「国立あおやぎ会」様の事例

「国立あおやぎ会」様では、清掃にかかる外注費の削減が大きな課題でした。メーカー直販価格で導入できる「RACLEBO」と補助金申請の提案により、複数台の清掃ロボット導入を実現。コストカットにつながったほか、場所や用途に応じた使い分けで業務効率アップにも貢献しています。
まとめ
国内で高齢化が進行する中、介護施設への需要はよりいっそう高まることが予想されます。業界の構造的問題および働き手となる若者の減少による人手不足を解決するためには、企業の組織体制および業務改善が必要です。
人手不足による従業員の負担増加や業務効率の改善などの悩みを抱えている場合は、ぜひ「ROBOTI」にご相談ください。介護施設ごとの状況を踏まえ、予算内で課題が解決できる方法を提案します。些細な疑問・質問も喜んで承りますので、業務用配膳・清掃ロボットに興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
[出典]/厚生労働省/介護職員数の推移の更新(令和5年分)について/介護職員数の推移/https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/001362534.pdf/
[出典]/株式会社 東京商工リサーチ/2024年「老人福祉・介護事業」の倒産、休廃業・解散調査/https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200866_1527.html/
[出典]/厚生労働省/一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分)について/参考統計表/https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/001389804.pdf/
[出典]/厚生労働省/我が国の人口について/https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html/
[出典]/厚生労働省/介護労働の現状/https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000071241.pdf/
[出典]/厚生労働省/令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要/https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/22/dl/r04gaiyou.pdf/
[出典]/国税庁/令和4年分 民間給与実態統計調査/https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan/gaiyou/2022.htm/