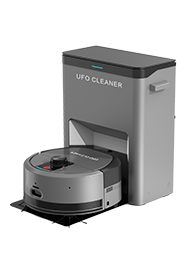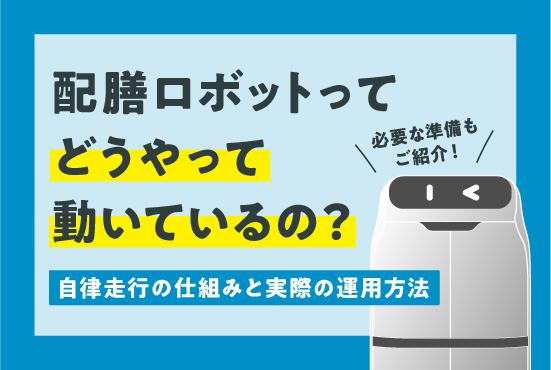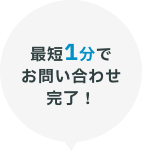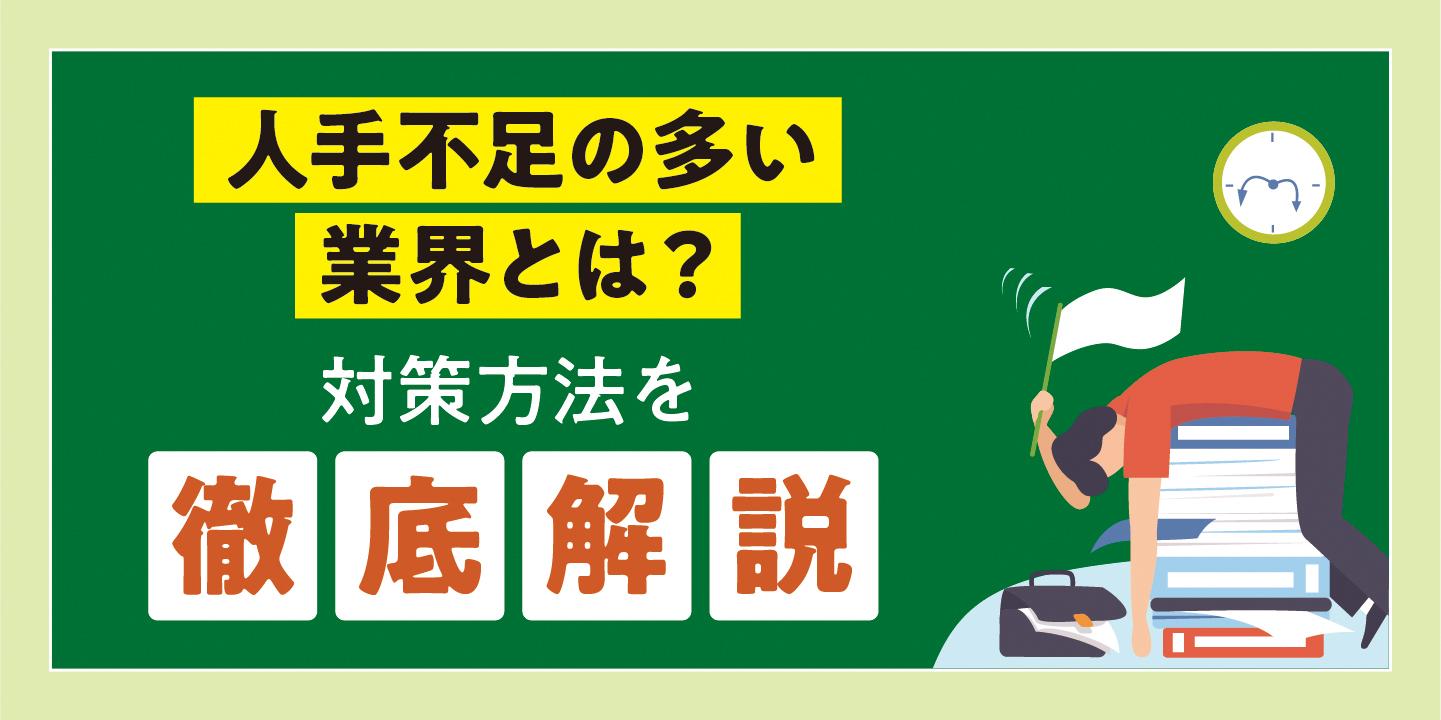
若者はどこへ行った?人手不足の多い業界とその対策を徹底解説
2025.03.01 (更新日:2025.05.27)
目次
年々深刻化する人手不足は、今や国内全体を悩ませる社会問題です。あらゆる業界で人手不足の割合が高止まりとなり、業務に支障をきたしたり、拡大にストップをかけたりする要因になっています。
今回は、国内における業界ごとの人手不足の動向についてまとめました。有効な対策方法も解説しますので、人手不足の現状をどうすればよいか悩んでいる企業・事業所の方はぜひご一読ください。
【2024年最新】人手不足の業界ランキング

まず、公式の調査データに基づく業界別の人手不足の状況をランキング形式でみていきましょう。
「人手不足に対する企業の動向調査」からみる業界別の人手不足
「株式会社帝国データバンク」が2024年10月に実施した「人手不足に対する企業の動向調査」における、人手の足りない業界ワースト10は以下のとおりです。
【正社員の人手不足が多い業界】
1.情報・サービス業:70.2%
2.メンテナンス・警備・検査業:69.7%
3.建設業:69.6%
4.金融業:67.1%
5.運輸・倉庫業:65.8%
6.旅館・ホテル業:62.9%
7.専門サービス業:59.1%
8.リース・賃貸業:56.8%
9.人材派遣・紹介業:56.7%
10.自動車・同部品小売業:56.3%
【非正規社員の人手不足が多い業界】
1.飲食店:64.3%
2.旅館・ホテル業:60.9%
3.人材派遣・紹介業:55.2%
4.メンテナンス・警備・検査業:54.1%
5.娯楽サービス業:52.0%
6.飲食料品小売業:49.7%
7.各種商品小売業:48.9%
8.金融業:43.8%
9.繊維・繊維製品・服飾品小売業:43.8%
10.教育サービス業:43.5%
正社員だと、専門的な知識やスキルを有する人材が求められるIT関連や、労働環境が過酷になりがちな業界での人手不足が目立ちます。
一方、非正規社員が不足しているのは、飲食店や旅館・ホテル業、人材派遣・紹介といった業界です。上記の業界は、少数の正社員と大多数を占めるアルバイト・パートタイム労働者という構成で運営されているケースが多い傾向にあります。そのため、非正規社員の人手不足が深刻だという状況は、軽視できない問題です。
「未充足求人と欠損率」からみる業界別の人手不足
続いて、厚生労働省による「令和6年上半期雇用動向調査結果の概要」から、人手不足が深刻化する業界を紹介します。
【未充足求人の状況(欠員率)】
1.卸売業、小売業:2,706,000人(2.9%)
2.医療、福祉:2,695,000人(3.2%)
3.宿泊業、飲食サービス業:1,909,000人(4.4%)
4.製造業:1,682,000人(2.2%)
5.サービス業(他に分類されないもの):1,430,000人(3.0%)
なお、全業界を合計した未充足求人数は14,815,000人、欠員率は2.9%です。
人手不足が深刻化する業界ワースト3は?
ここまでのデータをまとめた結果、人手不足が深刻化している業界は以下のとおりです。
【人手不足の業界ワースト3】
1.医療・介護業界
2.宿泊・飲食サービス業
3.小売業
上記の業種は需要が高いにもかかわらず、雇用を増やせない、もしくは減ってしまっている状況です。需給ギャップが拡大する一方で、業務上の負担の大きさや労働環境・条件面の問題による離職率の増加も人手不足を加速化させています。
各業界で深刻化する「人手不足」問題

次に、国内全体における人手不足の現状とその背景を踏まえ、今後の見通しを探っていきましょう。
若者はどこへ行ったのか?
日本では、1995年以降、働き手となる64歳未満の人口が減少傾向です。少子高齢化が進行しており、将来的に人手不足がますます深刻化していくと予想されます。
また、時代の移り変わりとともに若者の価値観が変化したことも若者世代の人手が不足している一因です。働くことに自らの成長が重視されるようになり、企業とのミスマッチなどから、理想の労働環境を求めて転職・独立する人も少なくありません。そのうえ、メンタルヘルスの問題から、退職を余儀なくされる若者も増加しています。
結果として、各業界でメインの労働力となるはずの若者が減少し、人手不足が深刻化しているのです。
企業はなぜ従業員を雇わないのか?
近年、企業は人を「雇わない」のではなく、正しくは「雇えない」のが現状です。
現代の日本は、以前と社会の構造が変化し、事務職といった仕事に人気が集中しています。例えば、令和6年12月時点の事務従事者の有効求人倍率は0.45倍であり、求職者にとって非常に厳しい状況です。対して、販売やサービス業、製造・建設などの仕事の有効求人倍率は極めて高く、人手が不足していることが伺えます。その結果、人手を欲しがる業界・業種があるのに働き口が見つからないという「構造的失業」が加速度的に増加しました。
また、人手不足や物価上昇のあおり、政府の意向などを受け、企業は賃上げの動きをみせているものの、対応できているのは主に大企業のみです。人件費のさらなる増加が難しい中小企業では、働き手確保がより困難になっています。
くわえて、いわゆる「103万の壁」問題で、人手不足はさらに加速しました。所得が一定金額を超えると扶養控除が受けられなくなることから、働き控えする労働者もめずらしくありません。所得控除額の見直しが進められていますが、議論は停滞しており、現状では今後の先行きが不透明です。
こうした構造が変化しない限り、国内の人手不足を根本的に解消することは難しいでしょう。
人手不足はいつまで続く?
今後、国内の少子高齢化はますます深刻化すると予想されます。2025年以降は「団塊ジュニア」の多くが50歳以上になることから、多くの定年退職者が発生する見通しです。
それにくわえ、働き方や職業観の多様化から、今後のメインの働き手となる若者世代の確保がますます困難になるでしょう。
そうした背景から、人手不足はよりいっそう進行する可能性が高いといえます。日本の企業は従来の人口増加を前提とした成長・賃金システムを維持しているケースも多く、特に人件費を増やせない企業にとっては業務遂行および拡大の大きな痛手となるでしょう。
人手不足の業界が今後取り組むべき3つの対応策

深刻化する国内の人手不足を解消するには、従来のビジネスモデルの大きな変革が不可欠です。ここでは、人手不足にあえぐ業界が今後取り組むべき3つの対策方法を解説します。
幅広い雇用の確保
人手不足の直接的な解決策となるのが、新たな人材の確保です。賃上げ、福利厚生の充実などにより働きやすい労働環境に整備し、新卒・若手社員の採用を強化することが求められます。さらに社員教育制度を充実させ、未経験可の範囲を拡大すれば、今後の労働力アップにつながるでしょう。
あわせて、高齢者や子育て中の女性といった、働きたくても働けない層への働きかけも重要です。定年延長や再雇用・復職制度を充実させるとともに、時短勤務・リモートワークなどのフレキシブルな働き方を積極的に導入すれば、人手不足に歯止めがかけられます。
ただし、新たな労働者を雇用すると、その分求人コストと人件費がアップし、企業の負担が増える点に注意しなければなりません。また、雇用システムの変革には利害関係者の意向も重視されます。企業単位で改革を進めるには限界があるため、今後の労働力の自然流入の増加は一筋縄にはいきません。
労働生産性の向上
人手が足りなくても、個々の従業員の労働生産性を向上させればカバーすることが可能です。また、社会人の学び直しの重要性が高まる中、忙しさから時間が取れないケースも少なくありません。
上記を踏まえ、企業によるキャリアパスの透明化と、人的投資の増加が推奨されます。雇用側主導のリスキリング・リカレント教育の推進で自律的な学び直しを促し、社内でキャリアアップが目指せるシステムに変革すれば、マンパワーが強化できるでしょう。
従業員の技術向上および新たなスキルの獲得が進むことで、単純に労働生産性が向上するだけではなく、より高付加価値の業務へ従事できる労働力の創出にもつながります。
あわせて、社内コミュニケーションの活性化や、愛着が抱ける社内文化の醸成も必要です。気持ちよく働ける職場に整備することで、従業員エンゲージメントが向上し、就業意欲のアップと離職防止が図れます。
ただし、既存人材の質の向上は、短期的な施策だと一過性になりがちです。継続した対策が不可欠であり、その分コストも増加するため、リソースに余裕のない企業だと難しいかもしれません。
DXによる業務の効率化
限られた人手の中で、最小限のコストで最大限の効果を上げるには、業務効率化が重要なファクターとなります。人手不足が進む現代において業務効率化の鍵を握るのは「DX」です。
業務の一部をロボットやAIに代替させることで、既存人材を最大限に活かせるようになります。AI・ロボットはサービスの質が一定しており、夜間や休憩時間などのニッチな時間帯や危険な環境でも働けるため、人員はそのままに労働力が強化できるでしょう。
AI・ロボットなどのデジタル技術に代替できるノンコア業務(副業務)の代表格は、各種管理・経理業務や運搬・清掃などの単純作業です。ルーチンワークの負担を軽減すれば、業務フローが最適化します。その分、既存人材はコア業務に集中させられるため、人手の少ない企業でも効率よく回せるようになるはずです。
人手不足の解消にはサービスロボットの活用がおすすめ!

人手が足りない場合、新たに雇用を増やすと人件費がかかります。そもそも、あらゆる業界で人手不足が深刻化していることから、新たな人材を見つけるのは容易ではありません。
そんなときには、サービスロボットの活用がおすすめです。運搬・清掃といった単純かつ負担の大きい業務に割く人員の確保が難しいとお悩みなら「ROBOTI」へご相談ください。
導入の際はトライアルから設置・操作指導、保守・運用まで一気通貫でサポートします。買取のほか、初期費用が抑えられるレンタルサービスも実施中です。
なお、ROBOTI導入の際は各種助成金・補助金が申請できます。もちろん、複雑で煩わしい申請手続きもサポート可能です。
人手不足が多い医療・介護や宿泊・飲食サービス業、小売業におけるROBOTIの導入事例も多数。あらゆる業界の人手不足の解消および業務負担の軽減を実現しています。
まとめ
現代の人手不足を解消するには、DXによる業務効率化が最適解です。業務の一部をロボットに置き換えることで、人手を増やさずとも業務効率が向上します。従業員の負担軽減および既存リソースの有効活用になるため、働き方改革にもつながるでしょう。
運搬・清掃業務を代替するサービスロボットの導入なら「ROBOTI」へおまかせください。オフィスや工場はもちろん、幅広い業界に対応します。ロボットを活用して、いち早く省人化に取り組みましょう。
[出典]/株式会社帝国データバンク/業界動向/https://www.tdb.co.jp/report/industry//
[出典]/厚生労働省/令和6年上半期雇用動向調査結果の概要/https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/25-1/dl/kekka_gaiyo-04.pdf/
[出典]/厚生労働省/一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分)について/参考統計表/https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/001389804.pdf/