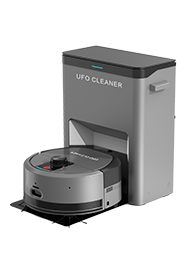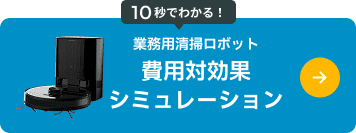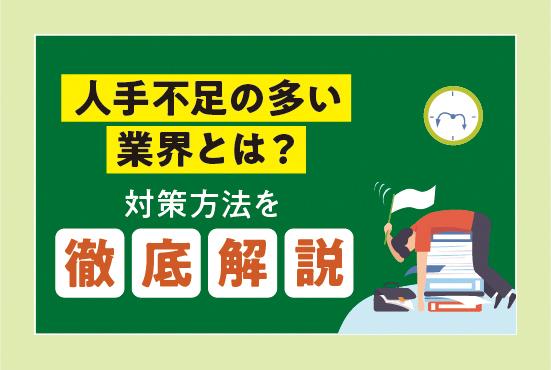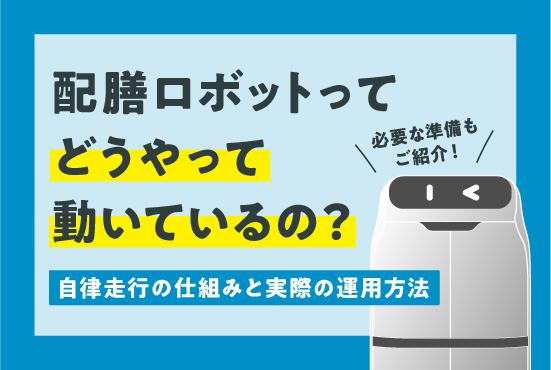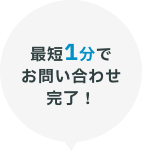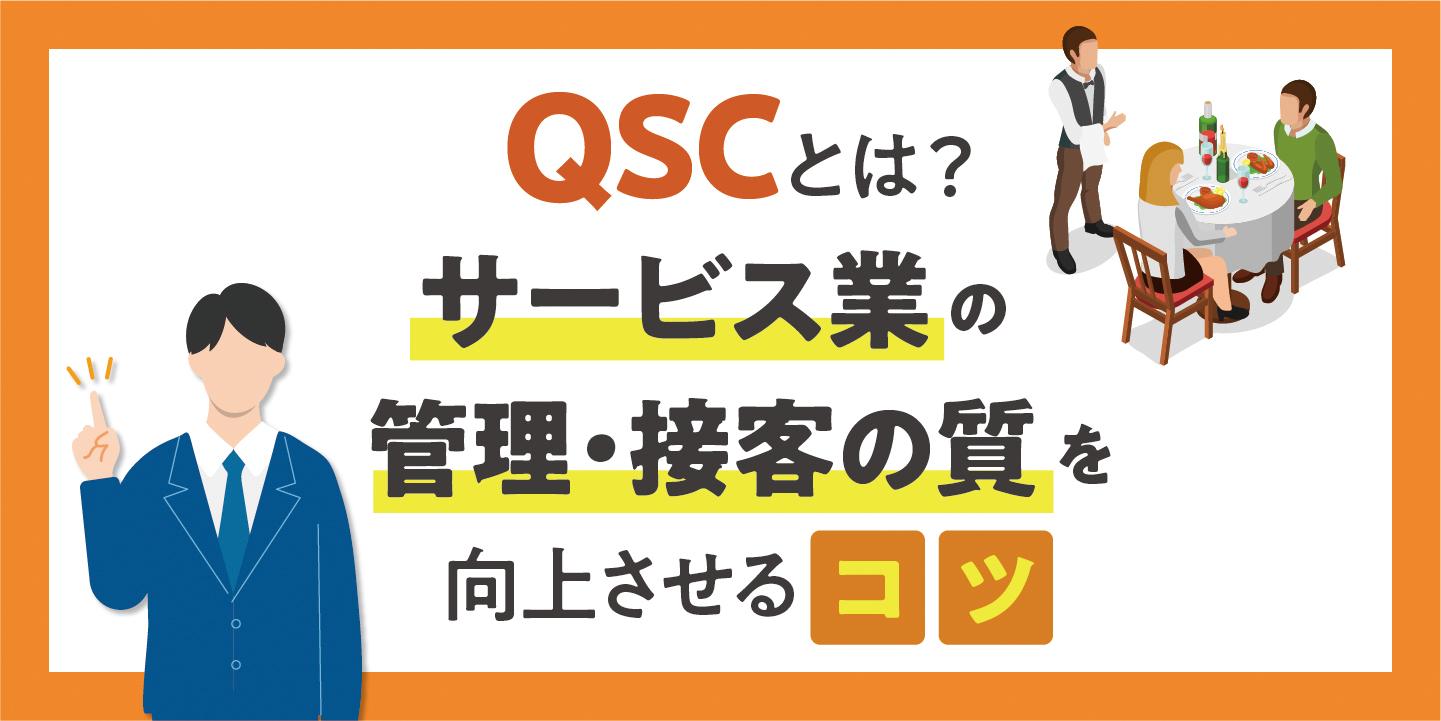
QSCとは?サービス業の管理・接客の質を向上させる戦略立案の5つのコツ
2025.07.10
目次
商品・サービス自体の評価は上々でも、顧客満足度が思うように上がらず、リピーターが増えないことに悩んでいませんか。その原因は「QSC」にあるかもしれません。QSCは、来店客が抱く印象を大きく左右する要素。特に、飲食業や小売・サービス業といった接客の多い業種で重視される概念であり、いかに向上させるかが課題となります。
今回は、店舗管理におけるQSCとはどのようなものなのかを徹底解説。成功戦略の具体例やポイントも紹介します。
QSCの意味

QSCとは「Quality」「Service」「Cleanliness」の3ワードの頭文字をとって作られた用語です。世界規模のハンバーガーチェーン「マクドナルド」の創業者の一人であるレイ・クロック氏が提唱したオペレーションマニュアルとして知られています。飲食店や小売店、宿泊施設などサービス業の店舗経営における基本理念といわれており、さまざまな企業がQSC向上に取り組んでいます。
まず、QSCの各ワードの意味をみていきましょう。
QSCの「Q」とは
QSCの「Q」は「Quality(クオリティ)」です。主に、消費者へ提供する商品・サービスの品質を指します。飲食店でいうと、メニューの種類や味にくわえ、見た目の美しさやボリューム、適切な温度設計などさまざまな要素を含みます。
品質は、商品・サービスへの満足度および価格設定を左右する重要なファクターです。ゆえに、企業や店舗には、常に品質の維持・向上に努めることが求められます。またチェーン展開している場合は、すべての店舗で品質が均一になるよう調整することも必要です。
QSCの「S」とは
QSCの「S」は「Service(サービス)」です。店舗で働く従業員による予約から入店、見送り、アフターフォローに至るまでの一連の接客の質を指します。具体的には、従業員の態度や身だしなみ、提供スピードなど、商品自体の品質によらない要素です。
どれほど高品質な商品・サービスでも、それを提供する接客の質が悪いと、顧客を満足させることはできません。利用者の満足度を高めるには、高品質な接客が提供できるオペレーションシステムの構築と、従業員教育の徹底が必要となります。
QSCの「C」とは
QSCの「C」は「Cleanliness(クレンリネス)」です。簡単にいうと、店内の清潔さを指します。
来店客が手に取ったり口にしたりする商品を取り扱う店舗内は、高水準の衛生管理が必須事項です。一箇所でも不衛生な箇所があると、利用客に不信感を抱かせる元になりかねません。メインフロアはもちろん、バックオフィスや調理場、トイレなど見えにくい場所も含む館内全体の清掃が不可欠です。
QSCの重要性

QSCは、顧客満足度や売上、集客など幅広いマーケティング戦略に影響を及ぼします。管理が徹底された店舗は多くの顧客を満足させ、売上アップに貢献するほか、リピーター・ファンの創出にも直結するからです。また、利用客により店舗のよい評判が口コミやSNSでのUGC(ユーザー生成コンテンツ)などで拡散されると、新規顧客の集客とさらなる売上向上につながります。
高品質な商品・サービスとオペレーション、清潔な環境は、どれか一つでも欠けてはならない要素です。つまり、利用客のイメージや居心地のよい環境が提供できるかどうかに店舗経営の成否がかかっているといっても過言ではありません。
近年注目される3つの「QSC+α」

近年、従来のQSCに加え「V」「H」「A」の3要素をプラスした概念が注目されています。以下では、それぞれのワードの意味を確認していきましょう。
QSC+V
QSC+Vの「V」とは「Value(付加価値)」を指します。商品やサービス、店舗のQSCが揃ったときに生まれる付加価値が、顧客のさらなる満足度向上につながるという考え方です。
QSC+Vは、その生みの親であるマクドナルドが現在掲げている理念でもあります。定義は業種や理念などによって変わりますが、自社のブランディングも踏まえて付加価値をつけることで、より高品質なQSCが提供できるでしょう。
QSC+H
QSC+Hの「H」とは「Hospitality(ホスピタリティ)」です。顧客を満足させる「おもてなしの心」を指します。
QSC+Hのポイントは、顧客一人ひとりのニーズに対応する「One to Oneマーケティング」を徹底すること。現代はパーソナライズされたサービスが求められる時代なので、一辺倒のQSCを提供するだけでは不十分です。個人によって異なる嗜好やコミュニケーションの仕方を把握し、商品・サービスや接客に取り入れることで、ホスピタリティの質が高まります。
QSC+A
QSC+Aの「A」とは「Atmosphere(店内の雰囲気)」です。店舗の外装・内装やスタッフの服装および配置など、一言で表現するのが難しい店内全体の「コンセプト」を表します。
調和のとれた雰囲気は、店舗独自の世界観を創り出し、それに共感するファンを引きつける魅力になります。ただし、好みの雰囲気は人それぞれであり、万人受けは極めて困難です。ターゲティングに合わせたコンセプトを設定し、特定の層の支持を集めましょう。
QSC管理を成功させる3つのポイント

QSC管理の成功の鍵をにぎるのは、次の3つのポイントです。
1.現場や顧客の声を取り入れる
2.マニュアル化する
3.ES(従業員満足度)を高める
1.現場や顧客の声を取り入れる
QSC対策を講じる際は、管理部門だけで検討するのではなく、現場の意見を積極的に取り入れることをおすすめします。顧客と最も身近な位置で働く従業員の声を聞くことで、実際の使用者の反応や改善ポイントがみえてくるからです。顧客の反応と併せて検討すれば、より効果的な戦略が立案できるほか、現場にも浸透しやすいでしょう。
2.マニュアル化する
QSC管理は、均一なQSC対策ができる仕組みづくりが必要です。口頭での説明や連絡のみでは、現場によって認識の差が生まれたり、ノウハウが属人化したりしかねません。QSCの向上策をマニュアル化し、すべての社員および現場で共有すれば、上質かつ均一なサービス提供が可能になります。
マニュアル化にあたっては、決定した戦略を反映した項目を作成し、確認・共有作業を業務フローに組み込むことで、現場へのスムーズな浸透が促せます。また、達成度を定期的にチェックし、きちんと実施できているかを確認することも大切です。
3.ES(従業員満足度)を高める
QSCの向上には、現場で働く従業員のモチベーションがキーポイントです。ES(従業員満足度)を高められれば、積極的な貢献が期待できます。
ES向上の具体策として挙げられるのは、給与アップといった労働条件の改善や休暇取得の推奨および福利厚生の充実、勤務時間の適正化などです。また、明るく清潔な労働環境は働きやすさにもつながるため、QSCを改善することで、ESも向上していくという好循環が生まれます。
QSCの向上の具体策

ここからは、QSC向上につながる5つの具体例を紹介します。
店内チェックシートの作成
QSCに関するチェックシートを作成し、現場で運用する施策です。チェックシートには、主に以下のような項目を設定します。
【クオリティに関するチェックリストの例】
- 業務の手順
- 品質や鮮度の基準
- 商品・サービス提供のスピード
【サービスに関するチェックリストの例】
- 接客時の挨拶と笑顔の励行
- 顧客の来店から案内までのオペレーション
- クレームや問い合わせ対応
【クレンリネスに関するチェックリストの例】
- 調度品や備品、トイレの清掃および点検の頻度
- 適切な清掃状態の基準
- 感染対策
一定の基準が設けられていれば、実施や点検・確認、振り返りなどが容易になり、QSCの徹底および全店舗における均一化が図れます。
ユーザーアンケートの実施
QSCの向上には、ユーザーアンケートの実施が効果的です。価格と品質、衛生環境の良し悪しは顧客がどう感じるかによって変わるため、消費者の視点に立って評価しなければなりません。
店内へのアンケート用紙設置や配布、DMおよびSNSを活用するなどして調査を実施し、顧客の声を集めましょう。さらに、顧客から評価されている点と改善が必要なポイントを把握・分析することで、QSCをよりよいものにしていけるはずです。
社内資格・制度の設置
QSC対策を現場へより深く浸透させるには、社内に専門の資格や制度を設置し、教育のプロフェッショナルを育成することが推奨されます。専門スタッフによる現場でのトレーニングとロールプレイングの実施で、最適な接客や環境整備が具体的にイメージしやすくなるでしょう。
実際に、大手コンビニチェーン「ファミリーマート」では、ストアスタッフ資格である「SST」や「エクセレントトレーナー」制度を採用していることで有名です。現場のスタッフ教育が充実するとともに、社員にスキルアップの機会を提供することで、従業員ロイヤリティの向上にもつながります。
コンテストやスタッフアワードの開催
QSCの向上にあたっては、独自の社内コンテストや表彰制度を設けることも有効な施策だといえます。同じ目標へ向けて現場全体で取り組み、他店舗と競争することで、一体感やモチベーションが高まるからです。受賞歴は店舗の実績となり、集客やイメージアップ戦略に役立つほか、企業の取り組みを対外的に示せるのでブランディング向上にも効果が期待できます。
ただし、表彰制度の公平性を担保するため、審査基準を明確に提示しなければなりません。また、競争が過激化すると情報・ノウハウ共有の妨げとなる事態が懸念されるので、社内全体への貢献度も審査項目に入れるといった工夫が求められます。
システムやサービスロボットの導入
小売店やサービス業は、業界を通して人手不足となっています。少ない人員で店舗を回すには、業務へのIT導入がおすすめです。例えば、サービス・接客業において、以下のようなITツールが役立ちます。
- 予約システム
- 案内・注文といったオペレーションシステム
- 配膳・清掃ロボット
業務のシステム化はすでに多くの現場で採用されているため、今後注目すべきはサービスロボットの活用です。店舗内の清掃や下げ膳といった単純ながら重労働の業務をロボットで代替することで、サービスの均一化と従業員の負担軽減、人件費の削減につながります。
清掃・配膳ロボットの導入なら「ROBOTI」

QSCの徹底は、利用客にとってイメージや居心地がよい店舗づくりにつながり、売上アップにも貢献します。また、働きやすく、成果が正当に評価される環境を整えることも、QSCの向上に欠かせない要素です。
従業員の労働環境および業務フロー改善、QSC向上を同時に実現させたいなら清掃・配膳ロボットの導入をおすすめします。
これから清掃・配膳ロボットの導入を検討するという方は、ぜひ「ROBOTI(ロボティ)」へご相談ください。ロボット選定から導入サポートまで、一気通貫で支援します。メーカー直販機種も多数でリーズナブルに導入できるほか、レンタルも可能です。
また、導入時の補助金の申請相談も受付中。業界ごとの課題にも精通するプロのスタッフが、最適なロボットと導入プランを提案します。